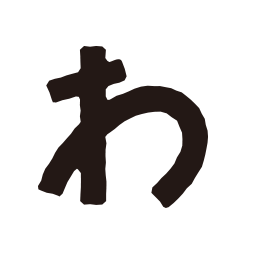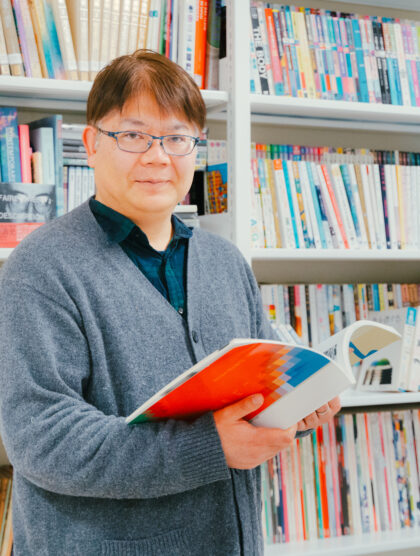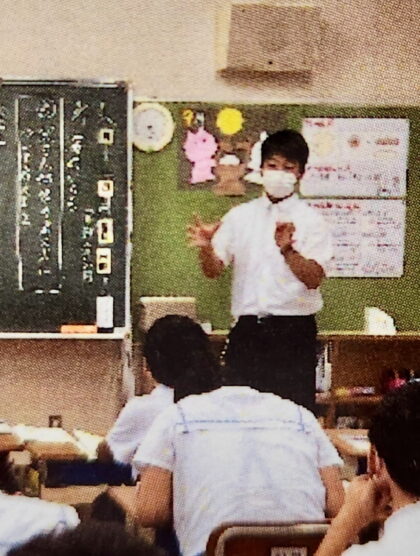2025.6.30
余さずいただく学び―鳥取市の日本料理店「みた」が教えてくれたものとは?

 わたしの地域に
わたしの地域に
ワンダーあらわる
鳥取大学の西前綾珠さんがフィールドワークで知ったのは、日本料理店「みた」で体験したマグロの頭身まで余さず味わう食文化と、田んぼで知った自然循環の学び。舌に残る旨味から農の手ざわりまで、五感を存分に使って、学生のまなざしで描きます。
私は地域学部の授業である「基礎ゼミ」内で行われた計四回のフィールドワークを通じて、「食」への興味関心を持っていた。なぜ「食」なのかというと、食べることが好きというのも理由の一つだが、フィールドワークに参加している人みんなが笑顔になる瞬間が、お味噌汁や豚汁、ピザなどを食べている時だったからだ。ご飯を食べると元気が湧き、「これ、おいしい!」「おかわりする?」などの会話も生まれ、「食べる」という行為が非常に面白く感じた。発見したことを以下に記していきたいと思う。
料理店「みた」で感じた食の喜び
2024年10月27日、私たちの基礎ゼミのメンバーは鳥取市の高級日本料理店「みた」を訪れた。私は高級料理店と聞くと、どっしりとした店構えでその一軒が目立っているようなイメージをしていたが、みたは質素な外観で、まさしく地元で愛されながら繁盛している店という風に思えた。
横開きのドアを開け、入口ののれんをくぐると、日本各地の銘酒を冷やした冷蔵ケースと赤いカウンター席が目に飛び込んできた。店内は市場のような香りが漂い、和の雰囲気がある。どんな料理が出てくるのか自然と想像したくなった。
みたさんは様々なこだわりがあることを教えてくださった。味の美味しさもそうだが、最も大切にしていることはお客さんに楽しんでもらえるような接客だという。みたさんが行っている、お客さんと話した内容や好き嫌いを都度メモし、次につなげられるようにしているという努力に私は敬服した。さらに、食事をする際のお客さんとの会話の中にも、みたさんがお客さんに楽しんでもらいたいという想いが込められているというのだから、尚更料理は美味しくなるだろう。そうした小さな努力からお客さんとの輪が広がっていくのだ。
お話を伺った後はコース料理を振舞っていただいた。
実際にこれから捌いてもらう鰆を持ち上げてみた。持ち上げた瞬間、中に身がぎっしり詰まっているだろう重さに私は驚いた。体長は私が両手を広げたぐらいの大きさであり、新鮮なもので、体は硬かった。漁師に捕獲されるまではこの大きな体で、雄大な日本海を悠々と泳いでいたと思うとなんだか不思議な感じがした。
そして、ついに「みた」の料理を食べる時が訪れた。

余さずいただくという発見
一品目は、先刻持ち上げた、鰆の刺身であった。鰆の頭を切り落とし、臓器を取り除き、三枚おろしにする瞬間をカウンターの目の前で披露していただいた。調理される前の姿から、皮一枚になる姿を見て、「生きていたもの」が「食べるもの」に変化したという事実を痛感させられた。
皮をバーナーで炙り、脂をふんだんに染み出させた刺身を、みた独自の醤油とポン酢にひたして食べると、頬が落ちるほどの旨味だった。私は、魚の美味しさを最大限に引き出した刺身に感嘆した。
そして、私の印象に最も残った品はマグロの料理だ。マグロの刺身は何度も食べたことはあるが、この料理は普通なら捨ててしまう頭から身を取り出してポン酢につけて食べる。私は、「食材を余すことなくいただく」ことを初めて経験した。マグロの頭から身を掻き出してそれを盛り付けるのだが、食べられる身が大量に出てきたことが想定外だった。普段なら廃棄しがちな量を最後まで活かしてこそ、本当の味わいになると感じた。素材の頭からしっぽまで残さずいただくという行為には、素材に対する敬意を大変に感じた。

自然と学びの循環
遡ること3週間前の10月5日、私たちは、鳥取県・智頭町「森のうまごや」の岩田和明さんを訪ねていた。岩田さんはご夫婦で、機械・化石燃料に頼らない馬耕という農法を行っている。私たちは稲刈りから稲を干すまでを教わったのだが、そこで私の今までの見方が変わる発見があった。
それは自然をそのまま活用している点だ。その一つに雑草がある。普通、田んぼの周りにある雑草は邪魔になるため、綺麗に除草して整えていることが多い。しかし、岩田さんはそれを敢えて残しており、雑草があるとエサを食べにくるカエルやイモリなどの生き物の住処になるのだという。生き物を発生させるためにわざわざ雑草を残しておく工夫に驚いた。
また、岩田さんは機械を一切使わずにすべて手作業で稲刈りを行っていた。機械を使用しないことで土が柔らかくなり自然のまま米を育てることができるという。自然の力だけで育てていると、人が手を加えても本来の姿が保たれる。田んぼを耕しても泥水ではなく綺麗な水のままなのはそのためだ。

私は、みたさんの「食材を余すことなくいただく」発想を知った時、この時の岩田さんの自然を丸ごと受け入れる姿勢を思い出した。両者には深い共通点があり、根底でつながっていると感じた。
フィールドワークに私は高校生の頃から興味を抱いていた。実際に参加してみると、驚きと発見の連続である。その土地の空気や人のあたたかさを感じ、同級生と共に会話をしながら活動することは非常に刺激的で、私にとって価値のある時間である。
余すことなくいただくという発想と自然を丸ごと受け入れる姿勢を知り、私は「私にとってのそれはなんだろう」と考えた。それは、フィールドワークで学んだことから、「私自身が変わる」ということだと思う。興味ある・ないに関わらず、たくさんの経験をし、知らなかったことを知った。自分が知りたかった、楽しかったと思えることを受け入れるのは簡単だが、そうは思えなかったこと、理解できなかったことを受け入れるのは難しい。それでも、自分にとって未知なことを自分なりに咀嚼し、自分なりの納得をして、変わっていくことが「余さずいただき、受け入れる」ということだと思う。一連のフィールドワークで、私はそんなことを考えた。
*この記事は、鳥取大学地域学部地域創造コース1年次必修科目「基礎ゼミ」(村田周祐先生, 2024年度)でのインタビューを基にしています。